身体の新陳代謝と冬バレエ〜出力の最大化と怪我の予防〜
- 2025.11.17
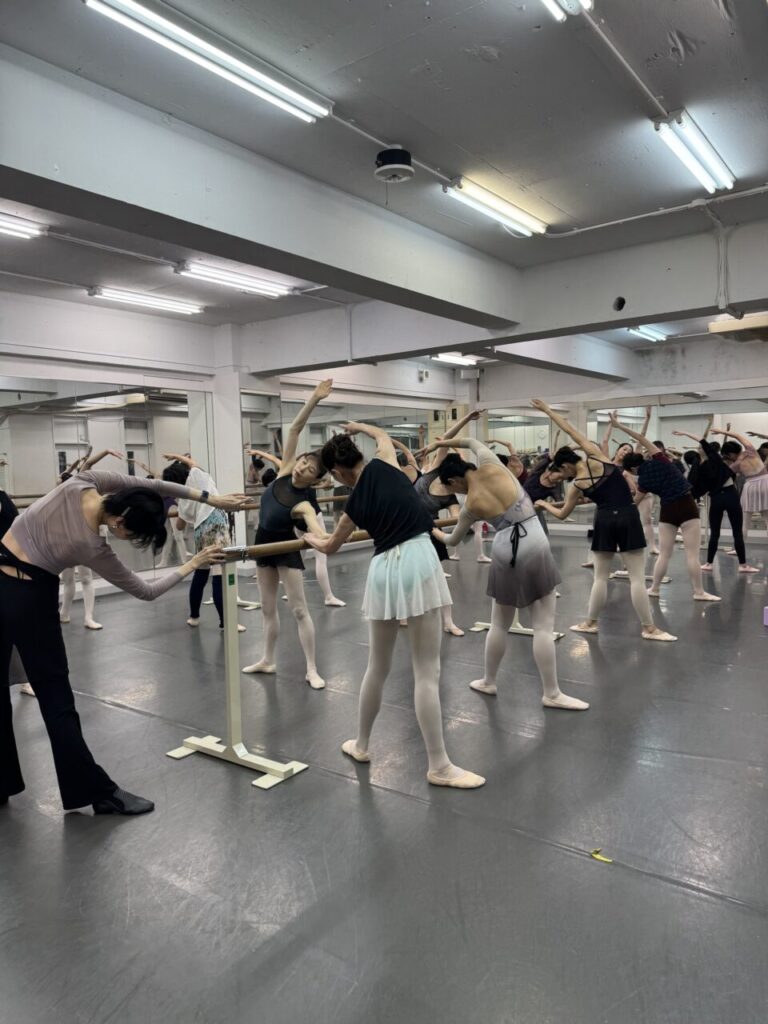
【このブログはアメブロで2回に分けて掲載したものを1回にまとめております。】
今回のブログは冬の過ごし方にも通ずる新陳代謝とバレエについての考察です。
長いので2回に分けて掲載しますので、ご興味ある方はお付き合いください。
だんだん寒くなるシーズンにバレエが上手くなるためには、まず上手くなれるようにトレーニングできる仕組みを作ることから始め他方が効率的な上達が図れます。
細かく分析したりメニューを紹介するスペースがないので、概要を記したので一読いただければ幸いです。
冬季の生理的背景(ざっくりと)
- 外気温が低いと末梢血管が収縮しやすく、筋温が下がる。関節・筋の粘性が上がる(筋肉が硬く感じる)。
- 日照時間が短くなると体内時計・睡眠・気分に影響しやすく、日常の非運動消費も下がりがちになる。
- 体は熱を作る方向に働き、褐色脂肪組織(BAT)やシバリング(小刻みな震え)による熱産生が増える。しかし、筋温が低いとパフォーマンスと代謝効率はガクッと落ちる。
つまり私たちが体感する現象そのものです。
では、バレエレッスンが冬の新陳代謝に及ぼす主な効果はどうでしょう。
即時効果として(1回のレッスン中)
-
筋温上昇が代謝率を向上させる:バーからセンターにかけて心拍数上昇し酸素摂取量が上がり、糖と脂質の酸化が促進する。
-
インスリン感受性の一時的改善:レッスン後4–24時間は血糖取り込みがよくなる。
-
交感神経トーン上昇:体熱産生と脂質動員が促進。ただし冷えた状態で急に激しく動くとケガのリスクが上がるので注意。
「脂質動員」とは、空腹時や運動時などで、エネルギーが不足した際に脂肪細胞に蓄えられている脂肪が分解されて血中に放出される現象です。
継続した場合の効果(数週間~数ヶ月継続)
-
除脂肪量アップ・筋酸化能(筋肉が酸素を使ってエネルギーを再合成する能力)アップ:中殿筋・ハムストリングス・下腿・体幹の持久系に影響が大きく安静時の代謝も底上げされます。
-
ミトコンドリア機能・毛細血管化向上:脂質代謝の比率が上がり、冬太りを抑制する効果がある。
-
姿勢・呼吸機能改善:横隔膜&肋間筋を大きく使うよう意識すると、安静時のエネルギー効率も改善する。
代謝の向上は冬太りの防止にも役立ちます。
ただし、レッスンをなんとなくこなすのではなく、一生懸命やって心拍数、筋温度を上げることが大事ですからね。
その日の体調のマックスを目指して頑張ることが明日につながるのです。
それでは冬ならではの“出力を最大化するコツ”は何でしょうか
1. ウォームアップを長めに(合計15–20分)
- 軽い全身リズム(屈伸・スキップ・カーフレイズ)
- ダイナミックモビリティ(ラジオ体操、股関節サークル、脊柱ロール、肩甲骨等)で可動域アップさせる。
- 皮膚温だけでなく筋温を上げるのが目的。運動が主役。
ジュニア子たちには何かゲームとかを取り入れるのもいいですね。
2. 強度設計(冬の代謝ブースト配分)
- 普段のレッスンに加えてコンディショニングやトレーニングを追加
- やや長めのセンターで運動後過剰酸素消費を狙う。
3. 栄養・水分
- レッスン前は炭水化物主体で良質なタンパク質を摂取するといい。
- レッスン中は常温水をこまめに飲む。四季を通じて水分補給は代謝を活性化させる。
- レッスン後は、タンパク質20〜30g+炭水化物で筋回復とグリコーゲン再補充。
- 日照が少ない時期はビタミンD不足に注意
4. 回復と体内時計
レッスン終了が夜遅い場合は、明るい照明を早めに落とし、リラックスして入浴。
可能なら午前中に自然光を浴びて概日リズムを整え、非運動性熱産生を底上げ。
これらのことはだいたいにおいては知識としてはあるのではないでしょうか。
ところが、知識はあっても継続できているかというと、自信を持ってイエスと答えられる方は少ないかもしれません。
まるでアスリートのようと思われる方もいるかもしれませんが、まだ続きがあります。
今回は前回のテーマのVol.2で、筋肉の「滑走性」についてです。
筋肉の滑走性という言葉はあまり耳にしないかもしれませんが、文字を見るとおよその想像がつくのではないでしょうか?
あまり長くならないように頑張ってまとめてみますので、よろしければご一読ください。
1. 「滑走性」とは何か
-
筋・腱・筋膜(層と層)の相対滑りのしやすさのこと。
-
組織の間にあるヒアルロン酸(HA)を含む基質と微小な水分層が“潤滑剤”。
-
滑走性が落ちる=粘性が上がるそして摩擦が上がる → 組織にせん断ストレスが溜まり、張り・痛み・可動域低下に直結する。
2. 代謝が滑走性に及ぼすメカニズム(冬に起こりやすいこと)
① 温度(筋温)
-
代謝が立ち上がると筋温上昇しヒアルロン酸(HA)の粘度が下がる。効果として層間が滑りやすくなる。
-
逆に冷えは粘性が上がってしまい弾性が下がるので「ギシギシ」感。冬はここが最大の敵。
② 末梢循環・水分移動
-
運動で交感・代謝が上がると血流と間質水の更新が進み、潤滑層が整う。
-
脱水・低糖(エネルギー不足)は基質がドロッとして、滑走性が低下してしまう。
③ pH・代謝産物
-
立ち上がり直後の酸性化(乳酸等)は一時的に粘性アップの要因。連続的で軽い運動をするとクリアされ滑りが改善。
-
いきなり高速・高強度の運動は酸性化だけ起こし温度と循環が追いつかないと滑走性はむしろ悪化。
④ 神経筋トーン(自律神経)
-
交感優位が過度だと筋緊張増加→層間圧迫で滑りにくい。
-
呼吸で副交感を少し入れるとトーンが下がり、滑走面の圧迫が減る。
神経筋トーン(筋緊張)とは、筋肉がリラックスした状態でも保たれている、神経と筋肉による一定の緊張状態を指します。
これは姿勢保持や体温調節に重要であり、筋の粘弾性と、伸張反射による反射的な収縮の2つのメカニズムから成り立っています。
繰り返しになりますが、筋肉の滑走性が向上すると関節の動きがスムーズになり、可動域が広がります。
逆に滑走性が低下すると筋肉と組織の間の摩擦が増え、関節の動きが悪くなり、痛みや機能障害につながる可能性があります。
この滑走性は、筋膜など筋肉を包む組織の癒着がない状態を指し、ストレッチやマッサージ、適度な運動によって改善されるのです。
ここまで読んでいただけたら、ウォームアップの重要性がお分かりになるのではないでしょうか?
では、筋肉の滑走性を高めるにはどうしたらいいかというと、まずこれには基本原理があります。
滑走性は「筋肉・腱・筋膜の層どうしがスムーズに動く状態」であり、これを改善するには以下の要件が必要です。
-
筋温を上げる(血流・代謝を上げる)
-
層間に“せん断刺激(ずれ)”を与える
-
一定リズムで“止めずに動かす”
具体的に例を挙げるならば、ラジオ体操のような全身の関節を動かしながら筋肉の伸張収縮を繰り返す運動がわかりやすいと思います。
軽いジョギングや膝を高く上げるスキップ、リズミカルなスクワットやランジなども効果的です。
バレエにおいてストレッチはとても重要ではありますが、筋肉の滑走性を向上させるためにはスタティックなストレッチは効率が悪く向きません。
当スタジオのボディワークバレエコンディショニングでは、筋肉に刺激が入りやすくするためのコンディショニングという位置付けでもあります。
バレエに特化した筋肉や関節周りのリリースと伸縮に重きを置いています。
クラスの前でも後でも効果が感じられるよう組み立てています。
実はラジオ体操は非常に優秀な全身動的ウォームアップです。
-
肩甲帯・脊柱・股関節・足関節の多関節運動
-
関節包・筋膜・筋肉の滑走面をまんべんなく動かす
-
一定リズムで止めずに行うことで「粘性を“溶かす”」効果
これに加えてヒップサークル(腰をぐるぐる回す運動)、直立で方足を前後に大きく振り上げる振り子運動(バットマン)(左右30回ずつ)、カーフレイズ(1分)などを追加すると一段と滑走性が良くなります。
レッスン前の少しの時間を上手に活用すれば、レッスンが始まった時にはしっかり動けるようになるのです。
私のクラスで時々レッスンの最初にラジオ体操をやるのも少しでも筋肉の滑走性を高めるためです。
息切れや発汗はしっかり体を動かして温めている証拠です。
息切れや発汗を敬遠する方も見受けられますが、心臓だって筋肉ですし、呼吸を司る肺を動かしているのも呼吸筋という筋肉ですからね。
寒い季節だからこそ運動しましょう!
レッスン前のウォームアップが足りないと、レッスンの前半がウォームアップのためのレッスンになってしまいます。
すでに温まった身体で、プリエ、タンジュから筋肉を正しく使えるようになっていた方がバレエの上達には有効ですし、センターでは戸惑いなく全力が出せるようになります。
2回にわたるブログで書いたことは全年齢層の人に共通して言えることです。
若いからと油断していると怪我のリスクが高まってしましますし、パフォーマンスの質が落ちてしまいます。
秋冬は世界中のバレエ団が新シーズンが始まりダンサーもフレッシュに踊っている季節です。
私たちも楽しくバレエをするために、新陳代謝の向上と筋肉の滑走性を意識してレッスンしてみてはいかがでしょうか。